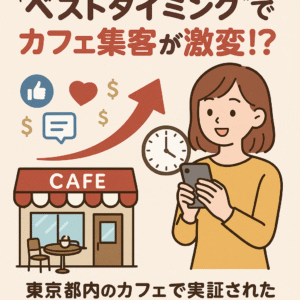【最新2024-2025年版】京都・東京で訪日外国人のSNS投稿がバズる理由とは?~インバウンド向け観光コンテンツと効果的なマーケティング施策を徹底解説~

2024年~2025年にかけて急増する訪日外国人がSNSで“バズる”理由を徹底解説。京都・東京で人気の体験や投稿傾向、国別の好み、プラットフォームごとの攻略法など、最新インバウンド施策のヒントが満載です。
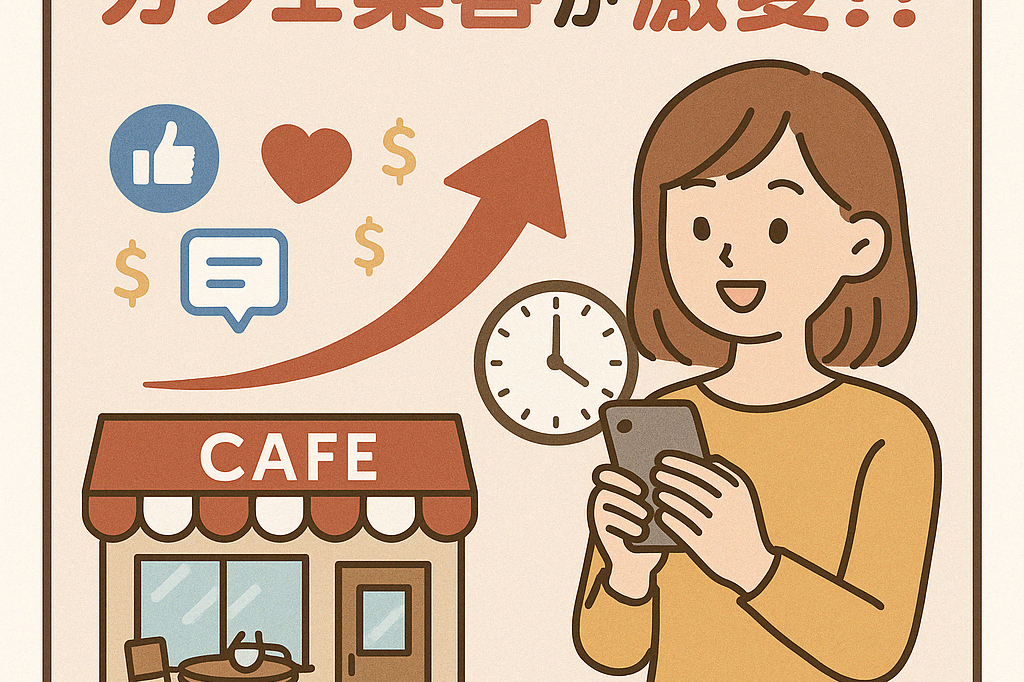
目次
- はじめに:2024-2025年におけるインバウンドとSNS投稿の現状
- SNSでバズる体験の5つの特徴
- 国別に違う人気コンテンツ
- プラットフォーム別の拡散傾向
- 投稿形式のトレンド:写真から動画へ
- 実際にバズったSNS投稿事例
- 訪日プロモーション施策立案に向けたポイント
- まとめ:日本の魅力を「バズる」形で世界へ
- 参考資料・出典
1. はじめに:2024-2025年におけるインバウンドとSNS投稿の現状
コロナ禍後の観光再開に伴い、2024年から2025年にかけて日本には世界各国から訪日客が再び集まっています。特に京都・東京は不動の人気を誇り、彼らの多くは旅の様子をSNSで発信。Instagram・TikTok・X(旧Twitter)などで日々投稿される写真や動画、ツイートの中には瞬く間に“バズ”を起こすものが少なくありません。
本記事では、京都や東京で**直近1年間(2024年4月~2025年4月)**に訪日外国人の間で話題となったSNS投稿を徹底分析。「着物×和菓子」「神社×アニメ聖地巡礼」など、どんな要素が組み合わさると海外のユーザーに受けやすいのか、国別・プラットフォーム別の特徴なども含めて詳しく解説します。今後、観光地や企業がインバウンド向けマーケティング施策を立案する際の参考にぜひお役立てください。
2. SNSでバズる体験の5つの特徴
1) 伝統文化体験のフォトジェニックな組み合わせ
古都・京都では着物をレンタルし、日本茶や和菓子を味わう優雅な伝統文化体験が非常に人気です。実際、「着物の着付け×茶道×フォトジェニックな観光スポット」という組み合わせの投稿で多くの「いいね!」を集める外国人インフルエンサーも。特に「着物×和菓子」や「着物×お抹茶」のように、色彩のコントラストが映える写真・動画はInstagramで拡散されやすい傾向があります。
2) ポップカルチャー×伝統風景のミックス
アニメやゲームなど日本のポップカルチャーと歴史ある名所を掛け合わせた投稿も注目度が高め。東京では『ラブライブ!』『君の名は。』のモデル地や神社を巡る「神社×アニメ聖地巡礼」が人気。神奈川・鎌倉の江ノ電踏切(『SLAM DUNK』聖地)には中国・台湾からファンが押し寄せ、SNSでも「台湾で最も有名な日本の踏切」として話題になりました。京都の伏見稲荷大社などでも、アニメの世界観を重ね合わせて楽しむ投稿が多数見られます。
3) ユニークな食体験・パフォーマンス
“食とエンタメ”が融合したコンテンツは爆発的に拡散されやすいです。京都の「火柱ラーメン」や奈良の高速餅つきパフォーマンスは、TikTokで何度もバズを起こした代表例。東京では浅草の食べ歩き(人形焼、雷おこしなど)や原宿のカラフルスイーツが人気を集めています。**「料理×ショー」**という演出要素が加わるほど拡散力は高まる傾向です。
4) アイコニックな景勝地と季節の風物詩
四季折々の絶景も鉄板のバズ要因。桜、紅葉、イルミネーションなどの季節限定イベントは、毎年訪日客によって無数に投稿され、繰り返し話題になります。京都の祇園白川や嵐山の桜、東京の目黒川や上野公園の桜並木などは訪日外国人が必ず撮影してSNSで共有する定番スポット。また、五重塔や鳥居といった日本を象徴するランドマークも外国人投稿で人気の被写体です。
5) 日本の日常に潜むサプライズ
高機能トイレや種類豊富な自販機、街中のネオン看板など、日本人にとっては当たり前の風景が外国人の目には魅力的に映ります。意外な日常シーンがSNSでバズるケースも多く、「#OnlyInJapan」といったハッシュタグで拡散されることもしばしば。東京の電車の時間厳守ぶりやコンビニの品揃えの豊富さなど、一見地味な要素が驚きのポイントになっています。
3. 国別に違う人気コンテンツ
中国・台湾圏
アニメ聖地巡礼やポップカルチャー系に対する反応が突出しています。鎌倉の『SLAM DUNK』踏切がSNS上でバズるなど、アニメ・漫画のロケ地を訪れる“聖地巡礼”が定番。中国本土のSNS規制の影響でInstagramやXを使えないユーザーも多いものの、日本で撮影したTikTok動画が転載されるなど、別の形で拡散されるケースもあります。
韓国
グルメや温泉、四季の風景が人気です。韓国人はInstagram利用率が高く、日本の美食巡りやカフェ巡り、桜や紅葉の写真を多数投稿。また温泉好きが多く、箱根や別府などの温泉地体験をシェアする人も少なくありません。リピーター率が高いため、奥深い日本文化や限定グッズ購入情報にも関心を持ちやすい傾向があります。
欧米(米国・欧州・豪州)
「畳・神社・侍」といった古き良き日本への憧れと、ハイテクやユニークな日常風景の両方に強い興味を示します。京都での寺社巡りや東京の浅草散策を写真に収める一方で、「日本のトイレがSFレベル」「日本のコンビニで1日生活チャレンジ」などの投稿も人気。特に欧米圏のユーザーは「伝統×モダンのコントラスト」を好む傾向があり、五重塔と高層ビルが同じフレームに収まる写真は「クール!」と絶賛されがちです。
東南アジア(タイ・シンガポール・インドネシア等)
雪景色や桜吹雪など、自国では味わえない四季の絶景とショッピングが主要な関心事。雪の中を走るローカル列車の写真や紅葉の名所情報は、とくに「いいね!」が集まりやすい傾向があります。一方、爆買いやブランド品購入をSNSでシェアする人も多いですが、“バズ”という点ではやはり非日常の景色や体験が強いです。
その他の地域
中東や南米などからの訪日客はまだ少なめですが、富裕層が東京の高級寿司店を訪れる投稿や、ブラジルのアニメファンが秋葉原でコスプレ写真をアップするなど、ニッチなコミュニティではそれぞれ話題になるケースが見られます。新たな市場にアプローチする場合は、その地域で人気の日本発コンテンツ(例:ブラジルなら『聖闘士星矢』)を活かしたプロモーションも有効でしょう。
4. プラットフォーム別の拡散傾向
写真と短尺動画が中心のビジュアル重視SNS。五重塔や鳥居のような“ザ・日本”な象徴写真、華やかな着物姿、繊細な和菓子など、絵になるコンテンツと相性抜群。近年は「リール(Reels)」で15~30秒のショート動画を投稿する外国人旅行者も増えており、フォトジェニックな写真だけでなく、ダイジェスト動画もバズのきっかけになっています。
TikTok
音楽とエフェクトを駆使した短尺動画プラットフォーム。驚きや意外性、エンタメ性の強いコンテンツほど拡散力が高く、「火柱ラーメン」「高速餅つき」など目を引くパフォーマンス動画が外国人ユーザーを中心にバズを連発。ハッシュタグチャレンジやデュエット機能で連鎖的に動画が増え、爆発的拡散を狙いやすいのが特徴です。
X(旧Twitter)
元々テキストベースのSNSですが、旅行中のリアルタイムな気づきや写真・動画を添えた投稿がバズる傾向があります。スレッド形式で「日本旅行で学んだこと10選」とまとめるなど、やや長文の情報提供も好まれるケースが増加。英語圏を中心に即時性・ニュース性のある話題(ハプニングなど)が特に伸びやすいです。
その他(YouTube・Facebookなど)
- YouTube: Vlog形式で10~20分程度の旅行記を投稿し、数万~数十万回再生を集める外国人が多数。
- Facebook: 欧米や東南アジアで依然利用が多く、文章をしっかり読むユーザー層に刺さりやすい。新潟県が雪景色を英語で紹介し、4千件以上の「いいね!」を獲得した事例も。
5. 投稿形式のトレンド:写真から動画へ
ショート動画の台頭
TikTokの世界的ブームを受け、InstagramリールやYouTubeショートなど、どのプラットフォームでも短尺動画が主流化。訪日客も旅の様子をその場で撮影し、15秒~30秒程度にまとめてアップするスタイルが増えています。「視覚・聴覚」の両面から訴求できるため、写真以上にバイラルしやすいのが特徴です。
写真投稿の工夫
写真の価値も依然健在。最近は**複数枚のアルバム投稿(カルーセル)**やパノラマ、360度写真などを組み合わせ、1日の観光ストーリーを演出する投稿が好まれています。シンプルに“映える1枚”を狙うだけでなく、複数枚で情報量を増やすことでエンゲージメント(保存・コメント)を高める手法が注目されています。
テキスト・字幕の役割
動画への英語字幕や、ミニブログ風の長文キャプションなど、テキスト要素も無視できません。日本語(ローマ字)を交えてユーモアを演出する投稿や、旅程や費用感を詳述するスレッド形式が一部の欧米ユーザーに支持を得ています。**「伝えたい情報は惜しまず書く」**ことで説得力が増し、バズにつながるケースが増加傾向にあります。
ライブ配信・ストーリーズ
インスタライブやYouTubeライブでリアルタイムの旅を配信する動きも活発。ただしライブ配信は一過性でアーカイブが残りにくい面もあるため、バズ狙いにはストーリーズのハイライト保存機能などを活用すると◎。企業や自治体がクイズやアンケートを組み合わせると、フォロワーとの双方向コミュニケーションにも役立ちます。
6. 実際にバズったSNS投稿事例
ケース1:「鯉のぼり投稿」で海外文化ファンを獲得
新潟県観光協会の公式Facebookが、夕焼け空を背景に500匹の鯉のぼりが泳ぐ写真と「300年以上続く伝統行事」といった説明文を投稿。約3,041件のいいね!と549件シェアを記録し、海外ユーザーから「美しい伝統だ」「見に行きたい」と絶賛の声が相次ぎました。**視覚的インパクト+データ(数字・歴史)**の組み合わせが成功のポイントとされています。
ケース2:カナダ人インフルエンサー「着物×ポケモン」
日本在住のインフルエンサーSharla☆シャーラさん(YouTube約70万人、Instagram約12万人)が、福島県浪江町の「ポケモン×道の駅」コラボイベントにて、着物姿でポケモン装飾を楽しむ写真を投稿。1.7万件以上の「いいね!」が付き、「着物とポケモンの組み合わせが斬新」「福島に行ってみたい」というコメントが数多く集まりました。
ケース3:TikTokで燃え上がる「炎のラーメン」
京都のラーメン店「麺屋 麺馬鹿一代」で、目の前で丼に火柱が立つ“炎のラーメン”パフォーマンスが大人気。訪れた米国人TikTokerの投稿が数日で数百万回再生を獲得し、海外ユーザーの「行きたい!」コメントが殺到。食×エンタメの強力なSNS映え効果を証明する好例となりました。
ケース4:外国人にも響いた「聖地巡礼」ブーム
2023年ヒットの映画『THE FIRST SLAM DUNK』効果で、鎌倉の江ノ電踏切(原作マンガの冒頭シーン)には中国や台湾から観光客が殺到。「#灌籃高手踏切」でSNSトレンド入りし、一時は地元住民が困惑するほどのオーバーツーリズムに。海外のアニメファンが「同じポーズ」を再現する投稿もSNSで多く見られました。
ケース5:京都の日常風景が生んだ小さなバズ
祇園の花見小路に「舞妓さんの無断撮影禁止」の看板が設置された様子を、欧米人観光客がX(旧Twitter)に投稿し数千のいいねを獲得。舞妓さんへのリスペクトを示す取り組みとして好意的に受け止められました。観光地のマナー啓発もSNSで評価される時代を象徴する事例です。
7. 訪日プロモーション施策立案に向けたポイント
- 体験コンテンツの組み合わせで魅力倍増
- 「着物×和菓子」「神社×アニメ」「グルメ×パフォーマンス」など、異なる要素を掛け合わせることでSNS映えしやすい内容に。
- 国別ターゲティング&多言語発信
- 中国・台湾向けならアニメ聖地情報を繁体字中国語で、韓国向けなら温泉やグルメ情報を韓国語で…といった具合に、ターゲットのSNS利用傾向と興味を踏まえた情報発信が有効。
- プラットフォームごとの最適演出
- Instagramには高品質な写真やリール、TikTokにはテンポ重視のショート動画、Xには速報的な小ネタやスレッド形式…といった形で使い分ける。
- インフルエンサーの活用
- 現地在住の外国人や海外で影響力のある旅行系YouTuber/TikTokerと提携し、体験を発信してもらうと効果大。発信内容がターゲットとマッチしているかも重要。
- ハッシュタグ戦略とUGC促進
- 「#TokyoMemories」「#HiddenKyoto」などの公式ハッシュタグを提示し、旅行者自身の投稿を誘導。フォトスポットやキャンペーンを設けるなど、ユーザー参加型で拡散を狙う。
- データ分析とフィードバック
- 投稿のエンゲージメントやコメント内容を精査し、次の施策に反映。特にInstagramのインサイト機能やSNS分析ツールを活用すると、ターゲット別の反応を客観的に把握できる。
8. まとめ:日本の魅力を「バズる」形で世界へ
京都・東京をはじめとする日本の観光地は、伝統文化・ポップカルチャー・季節の絶景・日常のユニークさなど、SNS映えする要素に溢れています。
2024年~2025年にかけて訪日外国人の数はさらに増加が予想され、彼らの“発信力”は観光地・企業にとって大きな追い風となるでしょう。
本記事で紹介した事例や施策ポイントを踏まえ、「どの国のユーザー」に「どんなコンテンツ」を「どのSNSで」届けるかを最適化し、より多くのバズ投稿を生み出してみてください。世界中の旅行者が「次は自分も体験したい!」と思うような魅力的なコンテンツを発信することが、インバウンド成功のカギとなります。
9. 参考資料・出典
- Kankou-One
- Honichi.com
- InfluencerMarketing-Company.com
- NewsDig(TBS)
- PR TIMES
- Dentsu-ho.com
- Ferret-plus.com
- Aiwafuku.com
- Japanticket.com
- Smrtkanko.com
- Twitter.com
本記事に掲載したデータや事例は、上記の観光マーケティング情報サイト・報道記事・インフルエンサー実績紹介など、信頼性のある公開情報をもとに再構成しています。SNSトレンドは日々変化しますが、根底にある「ユーザー心理のツボ」は普遍的。ぜひ本記事の内容を参考に、訪日インバウンド施策をブラッシュアップしてみてください。